〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
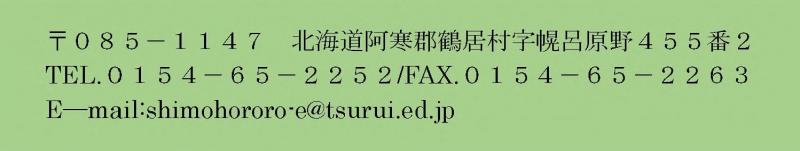
『努力』ってなんだろう?
校長 小 林 香 織
4月7日、鶴居村教育委員会教育長 村上明寛様、下幌呂小学校PTA会長 畠山 務様をはじめご来賓、保護者の皆様のご臨席を賜り、無事に令和7年度入学式を挙行することができました。改めましてお礼申し上げます。
☆ ☆ ☆
さて、入学式前の始業式では、昨年度末の修了式の時にも話をした『努力』について、子供たちに話をしました。
************************************************
3月の修了式に、コップとスポイトの話をしたのを覚えていますか?何かをできるようにするためには、コップにスポイトで水を一滴ずつためてためて・・・あふれるまで頑張ってためないと、努力の成果が現れないですよ。ためている最中は、どこまで貯まっているのかとか、あとどれくらい頑張れば良いのかはわからない。でもあきらめたら、せっかくためた水もこぼれてしまって、何も残らないですよ。「努力」ってそういうものだから、あきらめずに頑張りましょう。というお話でした。
新しい学年になり、新たにコップに水を貯め始める人もいれば、これまで頑張ってきたことを続けて頑張り、さらに大きなコップに水を貯める人もいると思います。どちらもやるよという人もいると思います。
新たなチャレンジをするにしても、今までのを続けるにしても、水を貯めている途中で成果が出てこないからといって泣いたり悔しがったりする必要はありません。あきらめずに水を貯め続けることが大事ですね。
実は、この「あきらめずに頑張る」という力も、大事な能力です。「能力」には、国語や算数のように、テストの点数などでどれくらいの力がついたか見える『認知能力』と、『努力』のように実際には見えないし、どのくらい力がついているか見えない『非認知能力』があります。
大人になって仕事をするときには、『認知能力』よりも努力する力や続ける力、人とコミュニケーションをとる力などの『非認知能力』が大事になってきます。そしてなかなか結果が出なくても、泣くのではなく、『泣いてても仕方がない。泣いてるくらいなら、次にどうするか考えて次に進まなきゃ!』と考えます。みなさんも、昨年度より1歳大人に近づきました。次に進むためにも、気持ちの切り替えを早くして、またコップに水を1滴ずつ貯めて、自分の力を高めていきましょう。
************************************************
私たち大人は、1回や2回頑張ったからといって、すぐに結果に結びつくものではないことは重々承知ですが、子供にとっては案外、「1回頑張った=結果が出る」と考えている事が多いようです。でも「コップに水を1滴ずつ貯めていくことが努力」というイメージが持てると、「どのくらい貯まったかなぁ」「まだまだ貯めなきゃダメかな」「もう少しであふれるかな」と、少し自分に期待を持ちながら、努力することを楽しむことができるようになります。
学校では子供たち一人一人が自信をもって、努力することを楽しみながら学びに取り組んでいけるよう、保護者・地域の皆様と連携を深めながら指導・支援をしていきます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。
鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。