〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
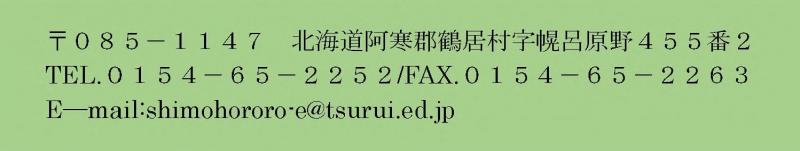
校長 小 林 香 織
13日の学芸発表会は、高松副村長、村上教育長はじめ多くのご来賓の皆様、そして保護者、地域の皆様に来校いただき、本当にありがとうございました。子供たちも、多くのお客様を前に少々プレッシャーを感じていたようですが、そのプレッシャーがほどよい緊張感となり、いつも以上に頑張ることができていたと思います。
☆ ☆ ☆
さて、本校では現在「令和の下幌呂型学校教育の創造~小規模校における個別最適な学び、協働的な学びを通して~」と題して、子供たちの生きる力を高めるための研究を進めています。この研究で主として取り上げている力は「自己調整能力」です。子供たちがこの力を身に付けるために、私たち教員はどのような単元を構想し、授業を進めていくかを研究しています。
実はこの「自己調整能力」は学習だけでなく、普段の生活の中でも必要な力です。具体的に「子供に『忘れ物をしない』力をつけたい」というシチュエーションで考えてみましょう。ここでの「自己調整能力」は最終的に「子供が忘れ物をしないように気をつける力を身に付ける」ことです。子供が書写の時間に使う書道セットを忘れたときに「担任」がどのように対応するかを考えてみたいと思います。
子供は担任の先生に「書道セットを忘れてしまいました。ごめんなさい。」と話すことでしょう。その言葉を受けての担任の先生はどうするでしょう?選択肢は3つ。
「A:お家の人に電話して持ってきてもらう」
「B:学校にある書道セットを貸す」
「C:書写の時間にどうするかを子供に問う」
どの選択肢が、子供にとって「自己調整能力」を身に付けるきっかけとなるのでしょうか?
私が担任ならば「C」を選択します。書道セットがなければ書写の時間は何もできませんから、書写はさせません。忘れ物をした責任は、子供自身がとるべきです。ですから、みんなが書道をしている間、なにかしらみんなと違うことをしなければなりません。恥ずかしいやら悔しいやらだと思いますが、この「恥ずかしい」「悔しい」という気持ちが、「次は忘れないぞ」という意欲に繋がります。
「それじゃ、子供にとってその1時間は無駄じゃないですか?」という声が聞こえてきそうですが、無駄にはなりません。なぜなら、AやBだと「子供自身が努力をしなくても、周りの大人が手を貸すことでなんとかなってしまう。」という経験を積ませるだけにしかならず、子供には求める力がつかないからです。
子供には「失敗から学ぶ」ということも必要です。失敗をしても責めず、かつ失敗を失敗で終わらせず、次に繋げてこそ「真の学び」があります。
☆ ☆ ☆
親にしてみれば、「子供に失敗させたくない」という気持ちが大きいと思いますが、失敗しないように…と一生手助けをし続けられるでしょうか?あと一歩だけ踏み出せば良いように下準備を全て大人がしてハードルを乗り越えさせたところで子供に力は付きません。真の力を子供に付けるためには、子供自身が責任を負い、次に繋がる行動を自分で考えて実践し続けていかなければならないのです。
人生で大きな失敗をしないために、日常の小さな失敗からたくさん学び、小さいうちに「自己調整能力」を身に付けられるように、家庭でも学校でもほんの少し工夫をしてみませんか?
鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。