〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
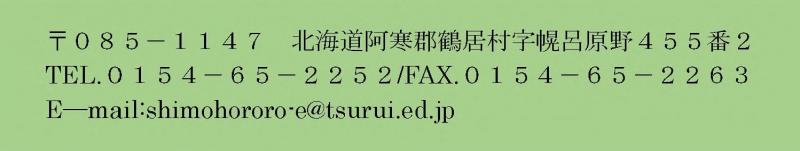
校長 小 林 香 織
6月末に6年生の修学旅行、先日は3~5年生の宿泊研修を無事終えることができました。行事が1つ終わると、なんとはなしに子供たちが少し成長したように感じます。それは、みんなのことを考えて準備を進めたり、予想外のことが起きてもみんなで対処を考えたりするなど、行事があるその日だけ特別に何かをするのではなく、子供たちのこれまでの学びが結実するからなのでしょう。
☆ ☆ ☆
明日から子供たちが待ちに待った夏休みです。夏休みの計画を考えながら、夏休みだからこそのイベントを楽しみにしているようです。
そんな中、夏休みの自由研究などで、頭を悩ませている子供たちもいなくはありません。そんな時に保護者の皆さんはどうされていますか?たぶん、一緒に考えてあげたり、手伝ってあげたりしていませんか。
夏休みに限らずですが、子供たちにはある程度の「ほったらかし」が必要だと感じています。「ほったらかし」といわれると、放任のように感じられるかもしれませんが、違います。
子供が、自分のやりたいことをやりたいように夢中になってやっているときは、保護者は手も口も出さない。また、子供が行き詰まっているときは、相談には乗るけれど手は出さない。要は、子供がハードルや壁にぶつかっても、自分の力で乗り越えられるように「見守る」というスタンスを貫くということです。
乳幼児のときは、十分の十、手をかけなければなりませんが、年齢が上がるとともに、手をかける割合は減っていきます。1年生でも、“一緒にやってみる”や“お手本を見せる”ことで、自力でできることがどんどん増えていきます。6年生ともなれば、ほとんどが自力でできるようになります。
夏休みという長期のお休みだからこそ、子供自身が計画を立て、じっくり時間をかけて、夢中になって取り組む姿を「ほったらかし」してみませんか?
☆ ☆ ☆
十数年前にテレビの街頭インタビューで、「お子さんの面倒をを何歳まで見ますか?」という質問に、「えー、40歳くらい?」と笑顔で答えていたお母さんがいました。私は「えええええっ!?」と、テレビを二度見してしまいました。
子供が精神的にも、経済的にも自立するためには、「自分でなんとかする」という経験を小さなことから積んでいく必要があります。「這えば立て、立てば歩めの親心」といいますが反対に「かわいい子には旅をさせよ」という言葉もあります。子供を成長させるための「ほったらかし」おすゝめです。
鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。