〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
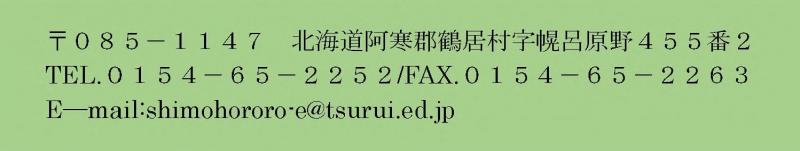
1学期最終日の7月20日(火)に7月集会を体育館で行いました。校長先生のお話があり,夏休みを迎えるにあたって子どもたちに3つのお願いをお話しました。一つ目は水の事故や交通事故などに気をつけて「自分のいのちを大切にすること」、二つ目は生活リズムを乱さないように「早寝、早起きをし、朝ごはんをしっかりとること」、三つ目は普段の家のお手伝いにプラス一つ「家のお手伝いをすること」をお願いしました。夏休みが終わり、元気な子どもたちが学校に集まることを待っています。

7月19日(月)に3年生~6年生の子どもたちは縦割班で夏休みの課題である交通安全ポスター作りの学習を行いました。まず、キャチフレーズを入れる事と絵や文字ははっきり大きめで色は4色ぐらいで抑えて描くことを条件に構想を練るこなどのポイントを確認しました。その後は班ごとにイラストやキャッチフレーズを考え、描きました。ポスターの仕上がりは夏休み後になります。どんな素晴らしいポスターになるのか楽しみです。


7月17日(土)午前中,2年ぶりとなる運動会を小学校単独で開催しました。残念ながら地域との合同運動会とまではなりませんでしたが,感染防止対策を講じ,競技数を減らすなど縮小して行いました。子どもたちは、『徒競走』や『湿原ソーラン』など,これまでの練習の成果を保護者や来賓の皆様に見ていただけるよう,精一杯がんばっていました。特に『紅白リレー』では白熱した走りが見られ,白組が僅差で勝ち,なかなか見応えのあるものでした。総合得点では赤組が優勝しました。晴天の中,盛会の内に第74回の下幌呂小学校大運動会を終了することができました。早朝よりたくさんの皆様にご来校をいただき,ご声援をいただいたおかげで子どもたちも張り切って参加できました。保護者の皆様方には,競技中や運動会終了後の用具等の準備や後始末にも御協力いただき,感謝申し上げます。ありがとうございました。






7月13日(火)に3年生~6年生の子どもたちは2回目のクラブ活動を行いました。ダンスクラブでは,2つのグループに分かれてそれぞれに洋楽の「コール・ミー・ベイビー」という曲に合わせてダンスの組立てを構想して踊りました。文芸クラブでは,3つのチームに分けてクラブ活動を行いました。一つ目のチームは「ファンタジー図鑑」作りで,文房具のホッチキスにまねたバッタなど色々な種類のキャラクターを作成しました。二つ目のチームは「冒険の絵本」作りで,猫などのイラストを描いてストーリーを構想しながら作成していました。三つ目チームは「物づくり」チームで,棚を作るために板を組み立てるのに電動ドリルでビス留めしたり,紙ヤスリで板を磨いたりしました。どのクラブも完成に向けて子どもたちは真剣に取り組んでいました。



給食メニューを紹介します。
7月14日(水) 7月15日(木) 7月16日(金)
・コーンチャーハン ・チーズパン ・炊き込みビビンバ
・たまごスープ ・ポークビーンズ ・白菜のスープ
・ナムル ・マッシュポテト ・ピリからきゅうり


今週もおいしい給食をいただきました。
7月6日(火)に3年生の子どもたちは社会科「お店で働く人と仕事」の学習でAコープ鶴居店におじゃまし,見学させていただきました。売り上げを高める工夫として,値段がわかりやすく表示されていることや,売り場がわかりやすいように案内板があること,産地や内容量などを示していることなどを子どもたちは発見していました。また,お店の人へのインタビューも行い,働く人の仕事内容や,一日の来店客数,値段の設定の仕方,売れ残りなどへの対応などを教えてもらいました。子どもたちは,ワークシートにメモしながら真剣に話を聞き,学びを深めていました。思いがけず,見学の最後に土産をもらい,子どもたちは大喜びでした。Aコープ鶴居店の皆さん,お忙しいところ本当にありがとうございました。


7月5日(月)に体育館で高学年の子どもたちが湿原ソーランを踊りました。運動会で踊る湿原ソーランのお手本として中学年や低学年の子どもたちに全力で踊りを披露しました。完成された湿原ソーランを見ることで運動会に向けてイメージを膨らませることができたよい発表でした。


7月1日(木)に授業参観及び学級懇談会を行いました。低学年の子どもたちは,保護者といっしょに1人の子どもがアートカードの画像の特徴を体で表したり,色や形を話すなどして,どのカードを表現しているかを当てる学習をしました。中学年の子どもたちは,膨らませたポリ袋に飾りをつけて大型扇風機や送風機を使って吹き上がる風にのせる学習をしました。5年生は,台風がどのように発生し動いていくのか,天気やそれに伴う被害について,タブレットPCを使って調べました。6年生は,試験管にある酢や石けん水,レモン水,石灰水にブルーベリー溶液を使って酸性なのかアルカリ性かを調べる実験を行いました。同じ酸性やアルカリ性でも試験管(対象物にブルーベリー溶液と混ざった液体)の色の濃さの違いで強弱があることや,アルカリ性の試験管に塩酸を加えると水溶液の色が変わることを学びました。
学級懇談会では,1学期の子どもの様子や夏休みの取り組みなど,保護者と意見交換を行いました。お忙しい中,多くの皆様に来校をいただきありがとうございました。




7月1日(木)にひがし北海道クレインズの選手とマネージャーさんが子どもたちの登校を見守りながら朝の挨拶をしてくれました。コロナ禍,学校行事や日常生活への影響を危惧され,少しでも子どもたちや地域住民に明るくなってもらうために来校されました。ひがし北海道クレインズの選手とマネージャーさんに感謝を申し上げます。


給食メニューを紹介します。
7月7日(水) 7月8日(木) 7月9日(金)
・たけのこごはん ・ごはん ・ミートスパゲティ
・小松菜の味噌汁 ・ふの味噌汁 ・ヨーグルトあえ
・きんぴらごぼう ・豚じゃがキムチの煮物
・七夕ゼリー ・ごまあえ



今週もおいしい給食をいただきました。
6月28日(月)に児童会が主体となって運動会の発会式を体育館で行いました。発会式にあたって校長先生から「運動会を成功させるために一人一人の役割が大事。その自分の役割を考えながら頑張ってください。」というお話をいただきました。次に,運動会担当の先生から実行委員会の役割等が説明され,その後子どもたちは各実行委員会(児童会三役、放送・応援・用具実行委員会)ごとに分かれて,計画・目標・活動のきまりや注意点を決めていました。また,6月30日(水)には紅白結団式を行い,赤組・白組の団長,副団長,団員,種目リーダーが発表され、子どもたちはそれぞれの団の目標を立てました。後日,会議で競技の作戦や自主練習の計画を立て,入退場などの種目の確認など行う見込みです。いよいよ,子どもたちの運動会へ動き始めました。




6月25日(金)に体育館で児童朝会を行いました。はじめに中学年の子どもたちがリコーダーの演奏とダンスの発表会を行いました。楽器演奏では,「ゆかいな牧場」という曲を上手にリコーダーで演奏し,ダンスは曲に合わせて全身を使って表現を披露しました。最後に,会場のみんなも一緒にダンスをして楽しみました。最後に,児童会三役から今年度の運動会のスローガンが発表されました。今回は,「仲間と団結!勝利を掴み取れ!!」です。17日,運動会に適した天気になることを祈っています。


6月23日(水)に3年生~6年生の子どもたちが,ダンスクラブと文芸クラブに分かれてクラブ活動を行いました。文芸クラブは,図書室で文房具をまねた生き物を描く「ファンタジー図鑑」や「冒険の絵本」をつくるグループと,児童玄関前で「物づくり」のグループに分かれて活動しました。本づくりでは,ストーリーや絵の構想を話し合って,物づくりでは棚を作るために板をノコギリで切る活動をしました。ダンスクラブでは,基本動作のスネーク,ラコステ,クラブなどを習得しながら洋楽に合わせて上手にフォーメーションダンスを踊りました。


6月22日(火)に子どもたちはタンチョウのえさとなるデントコーン畑でパオパオ(不織布)を外して雑草取りを行いました。デントコーンを保温していたパオパオ(不織布)を外すと,30~40cmの高さまで育ったデントコーンが現れ,生育観察を行いました。その後,どっさり生えた雑草を取り,溜まった雑草を運びました。教育委員会の方の説明をよく聞きながら進んで作業を行う子どもたちの姿がたくさんみられました。今年の夏,どれくらい成長するか楽しみです。


6月21日と22日,24日,30日に1時間目の授業が始まる前の時間を利用して,高学年の子どもたちが低学年に多目的室と体育館でよさこいソーランの踊りを教えました。運動会でも披露するよさこいソーランの振りや足のステップなど高学年の子どもたちは熱心に教えていました。低学年の子どもたちも習って一生懸命に踊っていました。下幌呂小学校の伝統芸能を引き継いでいく活動でした。運動会での発表をどうぞお楽しみに。


6月18日(金)に中学年と低学年の子どもたちが栄養教諭から食育学習を受けました。
中学年の子どもたちは「よく噛んで食べるとどんなよいことがあるかな?」を学習しました。よく噛んで食べると肥満防止や味覚の発達,言葉の発音がはっきりする,脳が発達する,歯の病気予防,ガン予防,胃のはたらきを良くする効果があることなどを学びました。噛む回数が多くないと食べられないスルメを使って子どもたちは時間をかけて食べる体験をしました。良く噛んで食べることを意識することが大切であることを学びました。
低学年の子どもたちは食べ物を栄養によって色分けをする学習を行いました。あかの仲間の食べ物(からだを大きくする肉や魚,卵,牛乳等)やみどりの仲間の食べ物(からだを元気に動くお手伝いをする果物や野菜,きのこ等),きいろの仲間の食べ物(からだを動かす元気のもとになる米やパン,いも,砂糖,油等)を栄養教諭が紹介した後,先生がいくつかの食べ物をあげて,どの色に当てはまるかの問題に子どもたちはチャレンジしました。カツオ節やもやしがどの色の食べ物にあたるかなど,難しい問題には迷わされていました。また,苦手な食べ物を克服するためにどうするかを考える学習も行いました。



鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。