〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
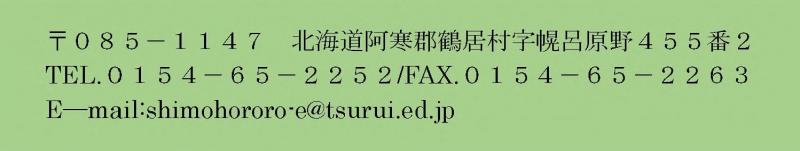
2月21日(水)の全校朝会で、6年生から卒業証書授与式で歌う曲が「ぼくらの日々」に決まったことが発表され、早速、全校児童で練習を行いました。歌詞の山場のところでクレッションド(次第に音声を強め気持ちがもりあがる)に注意して明るい表情で歌うことを学びました。歌詞を意識して歌うことができました。卒業証書授与式本番に向けて、合唱練習が続きます。


2月8・14・16日の3日間にわたり、業間運動の時間に体育館で送別球技大会を行いました。初日は6年生チーム対在校生3チームでボッチャの試合を行いました。結果は6年生チームが1勝2敗で惜敗でした。2日目はつなひき競技を行いました。6年生チームが全勝し、最上位学年の貫禄を見せつけました。3日目は6年生と障害物リレーを行いました。スケート記録会と同じ2チームで対抗し、6年生が投げたボールを大谷選手から贈られたグローブでキャッチしたり、6年生とチャンバラで一本とられるまでしたり、6年生のダンスをまねたりして競いました。もうすぐ卒業する6年生と楽しい思い出を作ることができました。この大会をもって今年度の業間運動を終了しました。





給食メニューを紹介します。
2月19日(月) 2月20日(火) 2月21日(水)
・ごはん ・きつねごはん ・ごはん
・ぶりカツ ・切干大根のカミカミサラダ ・ザンタレ
・ウインナーソテー ・豚汁 ・もやしとコーンのお浸し
・豚肉と野菜のスープ ・麩と葱の味噌汁


今週もおいしい給食をいただきました。
2月15日(木)に子どもたちが育てたコーンを、鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリさんへ寄贈しました。今年度も、子どもたちは種をまき、草むしり、コーンの刈り取り、収穫したコーン干し、コーンほぐしなど、例年どおりの取組を行い、無事に贈呈式を迎えることができました。後半はタンチョウや給餌の様子を観察しました。この日をもって今年度の「タンチョウのえさづくりプロジェクト:タンプロ」が終了しました。教育委員会をはじめ、たくさんの地域の方々に協力をいただきました。大変、ありがとうございました。



1月26日(金)と2月9日(金)に、釧路市阿寒ロイヤルバレイスキー場でスキー教室を行いました。昨年同様、教育委員会にお願いしてスキーの指導員の方2名にお手伝いをしていただくことができました。子どもたちの飲み込みの速さは凄く、みるみるうちにターンやブレーキが上達して、20回以上もリフトに乗って滑る子もいて、とても楽しく滑ることができていました。来年も上手にスキーができるといいですね。


鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。