〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。

〇令和7年度、新一年生1名を迎え、全校児童25名、教職員14名で下幌呂小学校の学校生活がスタートしました。本校の教育活動の様子は、トップページの「お知らせ」等でお伝えしていきます。
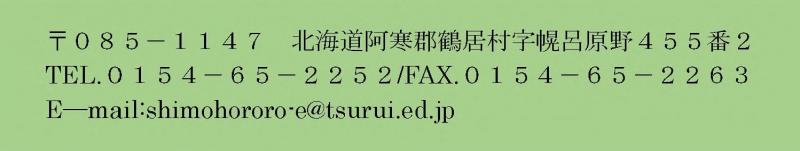
7月11日(木)~12日(金)に3・4・5年生が音別町体験学習センターへ宿泊研修旅行に行ってきました。
1日目の午前中は「札鶴ベニヤ白糠工場」で材木の加工工程やベニヤ製材工程を見学しました。午後からは音別こころみへ行き、マカロンを形取ったストラップ作りに挑戦しました。レクレーションでは、野外で鬼ごっこやハンカチおとし遊びをし、和室ではみんなでカルタを楽しみました。その後、夕食と入浴を済ませ、自由時間には和室でトランプなどを楽しみました。また、夜の星空探検ではたくさんの星や国際宇宙ステーションを見ることができました。
2日目の午前中には石けん作り体験をし、お昼に帰校しました。協力して楽しく活動する姿がたくさん見られた宿泊研修でした。




7月8日(月)、クラブ活動を行いました。
料理クラブはクレープを作りました。クレープにバナナとカラースプレー、生クリーム、チョコレートシロップをトッピングし、おいしく食べることができました。
ネイチャースポーツクラブは学校農園で育てているトウモロコシ付近の雑草取りを行い、その後体育館でフットサルやユニホック、キャッチバレーボールをしました。みんな楽しく活動する姿が見られました。




給食メニューを紹介します。
7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水)
・ごはん ・ごはん ・ごはん
・きのこスープ ・なめこと豆腐の味噌汁 ・かしわ汁
・ホイコーロー ・肉じゃが ・ホッケフライ
・わかめサラダ ・ぱりぱり漬け ・切り干し大根の煮物


今週もおいしい給食をいただきました。
7月4日(木)に授業参観及び学級懇談会を行いました。
1年生は国語で「話し言葉の文章と丁寧ないいかたの文章との違い」を学び、話し言葉の文章を丁寧ないいかたの文章に変換する学習を行いました。
2年生は国語で「だれかに言われて嬉しかった言葉」を書いて発表しました。
中学年は体育でティボール(止まっているボールを打って走る野球に似たスポーツ)を中学年対保護者で対戦しました。結果は捕球と送球が上手な保護者が勝ちました。得点を目指してたくさん走りました。
高学年は道徳で「『許さない』と『許す』を分ける線はどこにある?」を学習しました。自分が今後「許す」時にどんなことを大切にしたいか?大切にすべきか?について、自分の考えを発表しました。
学級懇談会では,1学期の子どもの様子や夏休みの取り組みなど、保護者と意見交換を行いました。お忙しい中、多くの皆様に来校をいただきありがとうございました。





7月1日(月)に、3年生は社会科「店で働く仕事」を学習するためにAコープ鶴居店へ行きました。
お店のバックヤード(倉庫、パッケージスペース)に入り、肉の加工の様子も見ることができました。お客さんに安心して喜んでもらえる商品提供の工夫についてお店の人から回答してもらい、今後の学習に役立つ情報を得ることができた社会見学でした。


楽しかった修学旅行の2日目。
朝一番におびひろ動物園を見学し、その後、自主研修で帯広市街にある駅前商店街などをまわり、おいしい物(ラーメン、カレーライス、お子様ランチ)を探して食べ,お土産を見て回るなど、五感を通した満足できる社会体験となりました。
2日間、天気に恵まれたすばらしい修学旅行となりました。6年生には,今回の体験をこれからの生活に生かして欲しいと思います。





6月25日(木)~26日(金)に、6年生は鶴居小学校と合同修学旅行に行ってきました。
1日目の午前中は「足寄動物化石博物館」での化石掘り出し体験や館内見学を行いました。お昼は音更町のエコロジーパークで昼食をとり、フワフワドームで遊びました。
午後からは川下り体験活動を行い、ゴムボートで十勝川を7km下りました。また、中州で十勝石をたくさん見つけることもできました。
ホテルでは、おいしい料理に舌鼓を打ち、他校の児童との交流をしながら楽しく過ごしました。昼間たくさん体を動かしたことで、夜はぐっすり休むことができました。




6月26日(水)、1年生が国語の時間で学んだことを職員室で発表しました。
自分の好きな趣味(一輪車、釣り)や動物(猫、うさぎ、犬)、おもちゃ(車)など、描いた絵を見せながら話すことができました。発表後、職員室の先生たちからは「話す速さと声の大きさが良く、相手を見て話す姿も素晴らしかったです。これからの学習でも学んだことを生かしてください。」と褒めていただきました。


給食メニューを紹介します。
6月24日(月) 6月25日(火) 6月26日(水)
・わかめのごはん ・手作りミルクパン ・ごはん
・芋と人参の味噌汁 ・鶏肉のポトフ ・キムチ汁
・豚肉と大根の煮物 ・ポークビーンズ ・麻婆豆腐
・ほうれん草とえのきのおひたし ・中華風サラダ


今週もおいしい給食をいただきました。
6月19日(水)、体育館で全校一斉に体力テスト(シャトルラン)を行いました。
リズムに合わせて体育館を往復する持久走ですが、子どもたちは記録を伸ばすために、一生懸命に走りました。最高回数は101回。来年も自分の記録を上回れるように体力をつけていきたいですね。


6月17日~19日の三日間、児童会二役を中心に緑の羽根募金が行われました。
緑の羽根募金で集まったお金は、身近な環境の緑化や水源林などの整備、地球環境問題の解決に向けた森林整備や緑化推進に使われます。たくさんの児童が、児童会二役による募金の呼びかけに笑顔で協力してくれました。
3日間合計で6,991円集まりました。ご協力ありがとうございました。


6月18日(火)、下幌呂小学校と鶴居小学校の6年生が修学旅行結団式を行いました。
最初に団長の校長先生から「準備8割、本番2割といわれます。物の準備、事の準備、身体と心の準備をして、健康な状態で修学旅行を迎えましょう」とお話がありました。その後自己紹介を兼ねて、修学旅行に向けて楽しみなことを発表し合いました。また、同じ部屋のメンバーでゲームを楽しむなど、交友を深めることができました。



6月17日(月)に1年生は鶴居村の栄養教諭の先生から、給食はどのようにできているのかを学びました。
食材の生産者さん、配達業者さん、調理員さんがどのような気持ちで給食に携わっているのかを学習しました。また、最後に「いただきます」「ごちそうさま」に込められた意味を学びました。1年生は苦手な食べ物も残さず、姿勢正しく給食を食べることを目標に立てることができました。


6月17日(月)に業間運動が行われました。
2グループ(ねこチームとねずみチーム)に分かれた子供たちは互いに向かい合って立ち、担当の先生が「ね、ね、ね、ねずみ!」と声をかけたら、ねずみチームがねこチームを追いかけ、「ね、ね、ね、ねこ!」と声をかけたら、ねこチームがねずみチームを追いかけます。タッチされないように集中して取り組む姿が見られました。


6月13日(木)、タンチョウのえさとなるデントコーン畑でパオパオ(不織布)を外して雑草取りを行いました。
デントコーンを保温していたパオパオ(不織布)を外すと、20cm高さのデントコーンが成長していました。子供たちは高学年を中心にテキパキ活動することができました。今年の夏、どれくらい成長するか楽しみです。


今年度も全校「体力テスト」に挑戦します。
6月12日(水)に体育館で反復横跳びや長座体前屈、上体起こし、立幅跳びの4種目を実施しました。
3つの縦割り班で取り組むことにより、上級生が下級生を取りまとめてスムーズに体力テストを進める姿が見られました。昨年の記録を上回ることを目標に、みんな頑張りました。



給食メニューを紹介します。
6月11日(月) 6月12日(火) 6月13日(水)
・手作り黒糖パン ・ごはん ・ごはん
・ミネストローネ ・若竹汁 ・野菜スープ
・ウィンナーの野菜炒め ・もやしつくねの照り焼き ・鶏肉の味噌焼き
・ひじきの煮物 ・ブロッコリーのおかか和え



今週もおいしい給食をいただきました。
6月8日(土)に、第77回下幌呂小学校運動会を行いました。
子どもたちは『徒競走』や『湿原ソーラン』など、これまでの練習の成果を保護者や地域の皆様に見ていただけるように精一杯がんばりました。
特に『紅白リレー』では白熱した走りが見られ、なんと!紅白同着という結果でした。総合得点では紅組が優勝しました。
保護者や地域の皆様には、早朝よりたくさんご来場いただき、種目(かけっこ、徒競走、玉入れ、大玉転がし)にも参加いただきました。また、用具の準備や後片付けにも御協力いただき、感謝申し上げます。ありがとうございました。






5月31日(金)に、3~6年生の子どもたちが第1回目のクラブ活動を行いました。この日は、部長・副部長、活動のめあてを決め、今後の計画を立てました。
今年度のクラブ活動は、フルーツポンチやドーナツ、ホットケーキなどのスイーツを料理する「料理クラブ」と、農園で作物を育てて収穫したり、鬼ごっこやボッチャ、フットサル、ミニバレーなどスポーツ活動をしたりして楽しむ「ネイチャースポーツクラブ」です。6月24日(月)から本格的に活動を開始します。


給食メニューを紹介します。
6月3日(月) 6月4日(火) 6月5日(水)
・ごはん ・ミートスパゲティ ・チキンピラフ
・しめじと玉葱の味噌汁 ・フルーツミックス ・ポトフ
・味噌おでん ・かぼちゃコロッケ
・和風サラダ


今週もおいしい給食をいただきました。
5月31日(金)に運動会に向けてグラウンドで「積み木遊び」と「リレー」の練習をしました。
前半の積み木遊びは紅白対抗でサイコロの出た色の積み木を一番上に積み上げ、同じ色のコーンをターンして次の人に交代するという競技で、30年以上前から続く下幌呂小学校の伝統的な種目です。初めて経験する1年生も真剣にルールを学び、しっかりと楽しみながら練習に挑戦しました。
後半のリレーでは、それぞれのスタート位置までの並び方を練習しました。


5月29日(水)に子どもたちはグラウンドで運動会種目の「湿原ソーラン」を練習しました。一年生にとっては初めてのよさこいソーラン。踊りに戸惑いながらも一生懸命に踊っていました。下幌呂小学校の伝統である湿原ソーランをどうぞお楽しみに。


5月28日(火)に、運動会種目「ゴールへGO!2024」と「地球をころがせ」の練習をしました。
「ゴールへGO!2024」は、スタートしてじゃんけんマンのところまで進み、じゃんけんマンにじゃんけんで勝つとそのまま次の障害物まで進むことができ、引き分け又は負けると遠回りして進むことになります。次の地点ではミニサッカーボールを蹴ってゴールに入れ、お玉にボールを乗せて落ちないようにゴールするという競技です。
「地球をころがせ」は保護者チームと児童チームが対抗する大玉ころがしです。大玉を素早く上手に転がす練習をしました。


今週の給食
給食メニューを紹介します。
5月27日(月) 5月28日(火) 5月29日(水)
・ポークピラフ ・ごはん ・ごはん
・枝豆サラダ ・ザンタレ ・ハンバーグ
・白菜スープ ・春雨炒め ・もやしのカレー炒め
・中華スープ ・コンソメスープ


今週もおいしい給食をいただきました。
5月24日(金)に北海道教育大学釧路校の新入生12名が来校し研修会を行いました。
最初に体育館で教育大生からの自己紹介があり、児童会長から歓迎の挨拶がありました。その後3校時から5校時まではそれぞれの学年に分かれてグ授業を参観しました。短い時間でしたが、子どもたちにとって素敵な思い出となりました。


5月23日(木)に子どもたちは学校農園やビニルハウスで野菜や果物の種まきと苗植えを行いました。
低学年は種イモを植え、二十日大根を種まきしました。
高学年は種イモやキャベツ、いちご、スイカ、きゅうり、トマト、ピーマンの苗を植え、人参の種をまきました。
たくさんの収穫を目指して大切に育てていきましょう。



5月23日(木)に1・2年生は湿原学習のためにバスで温根内ビジターセンターに行きました。子どもたちは湿原の中の遊歩道を歩き、自然とふれあいながらガイドの方から湿原について教わりました。「やちまなこ」や「やちぼうず」、「エンコウソウ」、「ヤマドリゼンマイ」、「ウグイス」、「たぬき」、「タンチョウ」などを実際に見て身近に広がる自然の宝庫である「釧路湿原」について学ぶことができました。


5月22日(水)に児童会が主体となって運動会の結団式が行われました。結団式の中で、校長先生からは運動会スローガンに謳われているように「心をひとつに勝利をめざしてやりきるために、一人一人がしっかり練習して運動会当日は全部の力を出し切れるように頑張ってください」というお話がありました。その後、紅組・白組のメンバーが発表され、子供たちはチームごとに目標を立て、心をひとつにしました。


給食メニューを紹介します。
5月20日(月) 5月21日(火) 5月22日(水)
・チキンのトマト煮 ・炊き込みビビンバ ・バターパン
・バターライス添え ・五目ビーフン ・クリームシチュー
・ミルクプリン ・野菜のスープ ・コーンソテー


今週もおいしい給食をいただきました。
5月17日(金)、1年生が職員室で大きな声をそろえて音読を発表しました。発表後、職員室の先生たちからは「はきはきした声でしっかり聞こえました。口をしっかり開いて姿勢がよいのが良かったです。」と褒められました。


5月16日(木)、4年生が社会科の見学学習で釧路広域連合清掃工場に行きました。
子どもたちは、可燃ごみの処理方法やごみの再利用について学びました。ごみ収集車からごみがピットに落ちる瞬間や、クレーンで大量のごみをつかんで引き上げる場面に驚いていました。身近なごみについて多くのことを学ぶことができました。


タンチョウのえさづくりプロジェクトが今年も始まりました。
5月15日(水)に地域の方にお借りしている畑に行き、タンチョウの餌となるデントコーンの種まきをしました。子供たちは、教育委員会の方の説明をよく聞きながら進んで肥料まきや種まきをし、パオパオ(不織布)張りまでの作業を行いました。たくさんの地域の方々に協力をいただいて終えることができました。ありがとうございました。


5月15日(水)に児童会二役より運動会のスローガン「心をひとつに 勝利をめざして やりきろう!」が発表されました。このスローガンには、①友達と一致団結して頑張ること、②最後まで楽しくやりきること、の2つの思いが込められています。児童会長から「運動会に向けて頑張りましょう」とお話がありました。今年の運動会は6月8日(土)の開催になります。


給食メニューを紹介します。
5月13日(月) 5月14日(火) 5月15日(水)
・カレーピラフ ・ごはん ・ごはん
・蟹風味サラダ ・ジンギスカン風煮 ・豆腐の野菜あんかけ
・とりごぼう汁 ・白菜とほうれん草のお浸し ・野菜のキムチ和え
・味噌けんちん汁 ・中華風スープ


今週もおいしい給食をいただきました。
5月10日(金)に教育委員会から講師の先生をお招きして、「タンチョウのえさづくりプロジェクト」の座学を行いました。
低学年はタンチョウが食べるもの、食べないもの、どのくらいのエサが必要かなど、タンチョウの生態について学習しました。また、タンチョウの模型から大きさや重さを疑似体験することでタンチョウについての学びを深めることができました。
中学年はタンチョウが季節ごとにどのような暮らしをしているかを学び、タンチョウ越冬分布調査について学びました。
高学年は、「なぜタンチョウを守るのか」、「もしタンチョウがいなくなったら」、「もしタンチョウだけ増えたら」など考える学習を行いました。最後に生きものや自然を守るために自分ができることを考えました。これからの活動が楽しみです。



5月8日(火)、3年生は社会科の学習で、鶴居市街の探検にいきました。お店や住宅、公共施設を見つけ、地図に場所を書き示しながら散策をしました。「このお店行ったことあるよ」「こんな場所にもあるんだね」と活動し、完成した地図から下幌呂との違いや共通点などを話し合い、土地の使われ方について学ぶことができました。


5月7日(火)、鶴居村駐在所長さんにご協力いただいき、防犯教室を行いました。
今回は、授業中に校内に不審者が侵入する想定での訓練でした。鶴居村駐在所長さんが不審者役となり、子どもたちは先生の指示に従って速やかに避難しました。避難後、鶴居村駐在所長さんからは「先生の指示に従って冷静に行動する事を忘れないで下さい。」というお話がありました。
また、学校外で不審者に遭遇した際の合言葉 「いか・の・お・す・し」(いか→行かない、の→乗らない、お→大声を出す、す→すぐにげる、し→しらせる)を確認しました。


5月7日(火)に全校朝会が行われました。校長先生から、「今の時期は一日の中で暑かったり寒かったりして季節の変化に体がついていけない時期なので、半袖の上にパーカーやカーデガンを着用するなど、気温の変化に対応できるようにしましょう」とお話がありました。その後、1年生に早く覚えてもらえるように、全員で校歌を歌いました。また、児童会長からあいさつ運動で特によかった児童の発表があり、全員で明るいあいさつができるように呼びかけました。


5月2日(木)に中学年は外国語活動の時間に今年度に新たに着任されたALTのマイク先生と一緒に英語を学習しました。
3年生は「英語のあいさつと世界のあいさつ」、4年生は「好きな活動や物と嫌いな活動や物(食べ物、スポーツ、遊び、趣味など)について英語で会話する」という学習を行いました。最後に、マイク先生の英語の掛け声でじゃんけんを行い、楽しく学習しました。


5月2日(木)の業間休みにグラウンドで、児童会二役が企画した今年度最初の全校外遊びを行いました。
一つのフィールド内に逃げる子どもたちを目がけて鬼がボールを転がして当てる転がしドッヂボールを行いました。1年生も楽しめるようにという二役の気持ちのこもった企画でした。晴天の中、全員で楽しく遊びました。


5月1日(水)に高学年の子どもたちは今年度着任された体育巡回専科先生から体育館で障害物競走を学習しました。
最初に柔軟体操をしてから前屈、開脚ストレッチをして十分動きやすくなった後、縄跳びの2重跳びに挑戦しました。次に平均台の両端から歩いて床に足をつけずに工夫してすれ違う運動をしました。最後に棒をおでこにあてて体を回転した後に平均台を通ってバーを跳び超えたりくぐったりする運動をしました。運動会の障害物競走に繋がる学習でした。



給食メニューを紹介します。
4月30日(火) 5月1日(水) 5月2日(木)
・スープスパゲティ ・ごはん ・ごはん
・パイナップルのヨーグルトあえ ・ホッケフライ ・肉団子の煮物
・ウインナーソテー ・枝豆とコーンのソテー
・坦々スープ ・芋とわかめの味噌汁


今週もおいしい給食をいただきました。
4月25日(木)に前期児童総会を行いました。児童会二役,文化,放送・保健委員会からみんなが協力し合い,学校生活を楽しくより良くしていく目標と活動計画を発表しました。子どもたちは,満足した表情で承認の拍手を送っていました。新年度の下幌呂小学校の児童会活動が活発に行われることを期待しています。


4月22日(月)、23日(火)の2日間、鶴居建設さんとあすなろ道路さんが本校のグラウンド整備作業を行ってくださいました。初日にあすなろ道路さんがグレーダーでグラウンドを削りながら平らにし、2日間かけて鶴居建設さんが転圧作業を行ってくれました。この2つの工程でとてもきれいなグラウンドになり、子どもたちが安全に活動することができるようになりました。鶴居建設さん、あすなろ道路さん、ありがとうございました。


給食メニューを紹介します。
4月22日(月) 4月23日(火) 4月24日(水)
・ハヤシライス ・きつねごはん ・ごはん
・はちみつレモンゼリー ・白菜とほうれん草のお浸し ・麻婆豆腐
・豚汁 ・野菜サラダ
・中華スープ


今週もおいしい給食をいただきました。
2年生の算数の学習の様子です。二桁のたし算のひっ算の仕方を考える学習を行いました。問題を確認した後、一の位の計算が二桁になるときは十の位に一繰り上げることを学びました。花丸をもらって喜ぶ子どもたちの姿が見られました。


1年生の国語の時間の様子です。「どろんこハリー」というペットの犬について描かれているお話を聞いて、自分が感じたことを全員発表しました。また、動物の鳴き声をもとに、場に適した声の大きさについて学びました。


4月17日(水)に鶴居村駐在所長さんや交通安全指導員の皆さん、パトロールボランティア、そして、保護者の方にご協力をいただいて交通安全教室が行われました。はじめに子どもたちは、トラックの運転席と助手席に座って死角体験をし、トラックの死角に入らないために近づかないことを学びました。次に、鶴居村駐在所長さんから、横断歩道の渡り方や自転車に乗る時に注意する事についての説明がありました。その後、子どもたちは実際に路上で交通安全指導を受けながら歩行や自転車走行を体験しました。今後も、子どもたちの安全意識を高めるとともに、学校・保護者・地域で子どもたちの安全を守っていきたいと思います。



4月14日(日)に授業参観・懇談会・PTA総会が行われました。授業参観では3〜6年生は国語の授業を、1〜2年生は算数の授業を公開しました。全体懇談会では、学校長から今年度の教育の概要や家庭・地域・教職員との連携の大切さについての説明がありました。PTA総会では、会長からPTAの意義や挨拶の大切さについてお話をいただきました。多くの皆様に来校いただきましたことに深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。


4月9日(火)より給食がスタートしました。「給食はやっぱりおいしい!」と、にこにこしながら食べる子どもたちの様子が日々見られています。1年生は、12日(金)から給食が始まりました。1年生にとって初めての給食は、今年は「ミルクパン」「ウインナーソテー」「ミネストーネ」「牛乳」でした。どの子もモリモリ給食を食べていました。おいしい給食に大満足の様子でした。


鶴居村3小学校で取り組んだ「みんなでムーブリズム運動動画コンテスト」において審査員特別賞を受賞しました。