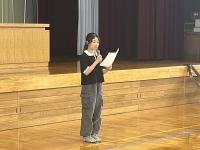鶴小 News & Topics
令和8年2月3日(火)スケート記録会(低学年)
天候に恵まれたスケート記録会。子供たちは50~500メートルの中から自分で選択した距離を一生懸命滑りました。中には転んでしまった子もいましたが、最後まで諦めずに滑ることができました。子供たちの顔には「やりきった」という達成感が見受けられました。
令和8年1月24日(土)今年度最後の土曜授業の日
地域の方も含め、約80名の方が学校に足を運んでくださいました。日頃からの学校へのご支援・ご協力に改めて感謝申し上げます。
少し変わった授業を行った2つの学年を紹介します。6年生が役場の保健師さんを先生として招き、「喫煙防止教室」を開催しました。写真やグラフなどを使って分かりやすくお話してくれました。5年生は和楽器の「琴」に親しむ授業でした。初めて琴に触れましたが、がんばって「さくら」を演奏しました。


1月集会
久しぶりの投稿になってしまい、大変申し訳ありません。冬休みが終わり、1月16日(金)から学校が始まりました。この日から転校生が2名入り、全校児童91人でのスタートになりました。(子どもたちが増える喜びをたくさん味わえた令和7年度になりました。)学校長のお話では冬休みを振り返ってよいことがあった人?にはたくさんの手があがり、がんばったことがあった人?にはよいことがあった人より手があがる人が減りました。そこで、後期後半(3学期)はがんばったことがあったと言える人がたくさんいる学校にしていけるといいですね。のお話にうなずきながら聞く子どもたちの姿がたくさん見られました。児童会代表(4年生)のお話では、後期後半にはスケート記録会や六年生を送る会などの大きな行事があるので一人一人目標や思いをもってがんばりましょう。といった内容をしっかりと話していた姿がとても立派でした。スケートリンクも無事完成し、毎日スケートの学習に楽しみながら一生懸命取り組む子どもたち。2月に行われるスケート記録会では練習の成果を十分に発揮できるのではと期待しています。
8月集会
8月22日(金)に夏休み明けの8月集会を行いました。心配された暑さは猛暑だった7月よりはだいぶ落ち着き、普段通りの鶴居村に戻った感じ(普段通りより涼しい)で、子どもたちも落ち着いた様子で会に臨むことができていました。この日の集会では転入児童1名の紹介と校長先生、児童会長のお話がありました。校長先生からはメリハリのある学校生活を8・9月は目指していきましょうというお話しがありました。児童会長からは、前期後半から後期にかけてたくさんの行事があるので団結力を高めていきましょうと話しました。夏休み明け、校長先生や児童会長の話を思い出し、規則正しい生活を取り戻して元気に過ごしていきましょう。
6年合同修学旅行
6月26日・27日に一泊二日で下幌呂小学校との村内合同修学旅行(十勝方面)に行ってきました。心配された天気も十勝に近づくほど良くなり、二日間すばらしい天気のなかで過ごすことができました。(日頃の行いの成果です)今年はバスガイドさんもいて、とても楽しく道中も過ごすことができました。(運転手さん、ガイドさん、添乗員さん本当にありがとうございました。)1日目の見学・体験ですが、まずは足寄動物化石博物館です。化石ほり体験に夢中になる子どもたちの姿が見られました。その後は、十勝エコロジーパークに移動して、昼食を食べ、フワフワドームで楽しく遊びました。次は1日目のメインの川下りです。みんなで、一生懸命こいで大きな川を下る体験は子どもたちの一体感が生まれるすばらしい体験になりました。その後はいよいよホテルです。広いお風呂においしいバイキング、自由時間の部屋交流と最高の時間があっという間に過ぎていきました。2日目は、まずは動物園から変更した児童会館ですが、最近リニューアルされ、エアホッケーやボルダリングもできるようになり、とても楽しく過ごすことができました。その後はグループごとの自主研修です。目的地や昼食場所を事前に調べ、ルート等を計画し、当日も子どもたちが主体的に動く姿がたくさん見られました。普段から仲のよい子どもたちですが、さらに絆を深めたこと、自分の学校だけでなく中学校で一緒になる下幌呂小学校の子どもたちとも絆を深められたとても有意義な修学旅行になりました。
5年宿泊体験学習
6月19日・20日に5年生が宿泊体験学習を行いました。宿泊場所は今年もネイパル厚岸さんを利用させていただきました。厚岸に着いて、海事記念館に行き、学芸員さんに展示物を教えていただきながら案内していただいたり、プラネタリウムを見たりしました。鶴居との文化や自然の違いを学ぶことができました。その後、ネイパル厚岸に移動して昼食を食べて、カヌー体験を行いました。初めてのカヌー体験の子も多かったですが、ここでも指導員の方がていねいに指導してくれて、最後まで楽しく活動することができました。その後はネイパルに戻って、焼き板クラフトづくりやキンボール体験など普段できない体験をたくさん行うことができました。(あいた時間は体育館でほぼおにごっこでしたね。)夕食や入浴、部屋交流など普段ではできない交流もたくさんできました。2日目は、部屋の片づけ等もしっかり行って、その後、標茶博物館「ニタイ・ト」に行きました。ここでも、学芸員さんにいろいろと教えていただくことができました。普段できない活動や交流、学習など貴重な時間を過ごし、帰ってきた子どもたちは疲れながらも充実した様子が見られました。
体力向上プロジェクト
6月16日(月)17日(火)の朝の時間に体力向上プロジェクトを行いました。今回の体力向上プロジェクトはなわとび検定へのチャレンジです。最初に先生から目標と説明がありました。そして2人1組でのなわとび検定の時間が始まりました。低学年の数を数えるのは高学年の子どもたちです。高学年の子どもたちが優しく「次は前跳び何回だよ。」等教えている姿がたくさん見られ、低学年の子どもたちのやる気を引き出していました。高学年の跳ぶときは、低学年も数えますが、一緒に自分自身でも数えます。低学年の子どもたちが見ている目の前で、お手本のように跳ぶ高学年の姿がかっこよかったです。まだ、これから何回かこのプロジェクトがあります。自分の記録をさらに伸ばせるようにがんばりましょう。
1年研究授業
6月11日(水)に1年生の研究授業を行いました。今年度の鶴居小学校の研究主題は「考えを形成しながら主体的に学ぶ子供の育成」です。研究の教科は国語科です。各学年の先生方が年に1回以上の研究授業を行う予定です。そのトップバッターとして今回は1年生の研究授業を行いました。今の時期の1年生はひらがなの読み、書きを覚え使い始めるころです。今回は「すずめのくらし」という説明文を読んで、どんな順番で文が書かれているか考える時間でした。最初に先生がこの時間でどんなことを学ぶか「見通し」をもたせ、目標となる「課題」を提示します。その課題に向かって1年生が今持っている力を最大限に発揮して学ぶ姿が見られていました。具体的には、すずめが活動している3つの写真から1つ選び、教科書の文を参考にしてどんな順番で文が書かれているか考え、先生が出すヒントカードをもとに、どこで、どんなことをしているか一人一人書くことができました。書く途中には子ども同士で交流する場面もあり、教え合う場面もたくさん見られました。最後はこの時間で学んだことの「振り返り」を行いました。1時間の振り返りは1年生にとってまだまだ難しいですが、これから経験を積むことでどんどん学びに対する振り返る力もついてくるのではと思います。子どもたちが飽きたり、あきらめたりしないよう準備していた先生とそれにこたえて一生懸命取り組んだ1年生、とてもすばらしかったです。
R7 鶴居小学校大運動会
5月31日(土)に大運動会を行いました。天候は曇り、気温は低めでしたが風はそれほどなく、徐々に暖かくなり、まずまずのコンディションで行うことができました。子どもたちは入場行進から元気にスタートを切り、開会式、エール交換へと向かいました。開会式では1年生の元気な誓いの言葉、そして児童会長がテーマ「全校で楽しみ、最後までやりきる運動会」について触れ、「勝ち負け関係なく、最後まで楽しみましょう。」と話しました。6年生の紅白団長を中心にどちらもとてもかっこよく、みんながしっかり声を出して行うエール交換はその後の競技への期待感が高まりました。その後は、みんなの力走が見られた各学年のかけっこ・徒競走、チームが一丸となってがんばった1~3年生の「綱引き」4~6年生の「台風の目」にたくさんの保護者の温かい声援が集まりました。そして、玉入れの合間にはダンスもしながら親子で楽しんだ玉入れ、高学年では親子で100個以上の玉が入ったり、小さなボーナスボックスに2個も玉が入るなど、おおいに盛り上がりました。そして、毎年恒例の鶴小名物にもなっている「タンチョウソーラン」高学年バージョンでは4~6年生のかっこいい演舞が光りました。また、全校バージョンでも全学年の息の合った元気な踊りが見られました。最後の競技は1~3年生のリレーと4~6年生のリレーです。この日のためにバトンパス等しっかり練習してきた成果を発揮し、どのチームも最後まであきらめずに走る姿が光っていました。閉会式、結果発表に喜んだり、悔しがったり姿がありましたが、真剣に取り組んでこその姿だと思いました。児童会副会長が、応援してくれた保護者・地域の方々や支えてくれた役員の方々にお礼を言い、「このがんばりをいろいろな場面につなげていきましょう。」と話しました。今年の鶴小大運動会も子どもたちが競技はもちろん、応援や係の仕事を一生懸命がんばったすばらしい運動会になりました。保護者・地域の方々最後まで子どもたちの応援、そして片づけ等もお手伝いいただき、本当にありがとうございました。
運動会総練習
5月28日(水)に運動会総練習を行いました。開閉会式の外での練習は初めてでしたが、しっかりと確認をしながら進めることができました。エール交換は両チームの応援団長を中心に元気なエール交換ができました。1年生の「かけっこ」、1~3年生の団体種目の「綱引き」、4~6年生の団体種目の「台風の目」全体の表現「タンチョウソーラン」は練習の成果を発揮した動きがたくさん見られました。また、総練習では係の仕事と種目を合わせる目的もあり、各係の仕事も確認しながら進めることができ、見通しをもった本番を迎えられそうです。明日はいよいよ運動会本番です。気温は低そうですが、子どもたちの元気な姿がたくさん見られる運動会になると思います。みなさん、温かい応援をよろしくお願いいたします。
コスモス種まき
5月19日(月)鶴居市街の2か所に1~3年生が村の花でもあるコスモスの種まきを行いました。種まきの場所につくと、鶴居市街自治会の方にあいさつをして、その後まき方を教えていただき、種をまきました。昨年までは全校で行っていましたが、今年度からは1~3年生で参加ということで、3年生がリーダーとなって進める姿がたくさん見られました。4~6年生は今年度から鶴居市街のマリーゴールド植えに参加します。全校で市街の美化活動に参加し、きれいな村づくりに少しでも貢献できること、子どもたちが参加することで地域の方々にも喜ばれる活動となっていることはとてもうれしいことです。秋にはきれいなコスモスが咲き、種取りにも参加する予定です。きれいなコスモスが咲いたらまたお知らせしたいと思います。
令和7年度がスタートしました
令和7年度がスタートして1ヶ月半ほどが経ちました。4月7日(月)に新学期がスタートし、着任式・始業式・入学式が行われました。新たに6名の教職員と9名の新入生、幌呂小学校からも9名が仲間入りし、活気のある4月になりました。5月連休が無事に過ぎ、今月末に控えた運動会に向けての練習が本格化しています。これからホームページの更新も本格化していきたいと思いますので、ぜひ目を通していただければありがたいです。令和7年度も鶴居小学校をよろしくお願いいたします。
令和6年度修了式・離任式
3月24日(月)に令和6年度の修了式・離任式を行いました。修了式では各学年児童全員の呼名と代表者1名が壇上で校長先生から修了証を受け取りました。どの学年の代表も緊張しながらもしっかりとした態度で受け取ることができました。式の中で校長先生のお話では各学年の良さと卒業式の在校生の姿のすばらしさ、良さを伸ばしてほしいこと、伝統を引き継いでほしいこと等の内容でした。うなずきながら聞く子どもたちの姿が見られました。また、各学年の代表児童1名ずつが今年度のがんばりと次年度の抱負を話しました。どの子も今年度目標をもってがんばっていたこと、次年度さらにがんばっていきたい気持ちが伝わる内容でした。修了式の後に離任式を行いました。今年度で異動する先生方の紹介とあいさつ、代表児童から花束贈呈、お礼の言葉が贈られました。春は別れと出会いの季節です。令和7年度は新たな鶴居小としてまたみなさんにいろいろな情報をお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
第102回卒業証書授与式
3月19日(水)に令和6年度第102回卒業証書授与式が行われました。卒業生8名全員が在校生、保護者、来賓の方々、教職員に見守られ、しっかりとした足取りで入場し、立派に卒業証書を受け取りました。証書を受け取る前に一人一人がステージ上で小学校生活で学んだこと、身に付いたこと、父さん母さんへの感謝の思いを話しました。どの子のスピーチも会場の人たちが思わず涙を流してしまうくらいとても感動的でした。よろこびの言葉・おくる言葉(呼びかけ)でも、在校生の子どもたち、卒業生がしっかりと思いをのせて言葉を届けることができました。式中の在校生の姿勢がすばらしかったことも6年生の門出を祝う気持ちのあらわれだと思います。式終了後は教室で最後の学活がありました。担任の先生の最後のメッセージをしっかりと聞く卒業生の姿がありました。最後に在校生、教職員による卒業生の見送りがあり、明るい日差しの中、明るい表情で見送られる卒業生の姿が印象的でした。最後の最後にPTAからのサプライズのギガ卒業証書の前で記念撮影を行いました。参加者全員の卒業生への感謝とこれからを応援する思い、そして卒業生の今までの小学校生活への感謝の気持ちとこれからの中学校生活をがんばろうと決意する思いがたくさん見られたすばらしい卒業式の一日になりました。
6年生を送る会
3月4日(火)に6年生を送る会を行いました。今までお世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えようと実行委員会で計画し、各学年が出し物を準備してこの日を迎えました。当日は実行委員会の子たちがあいさつや司会を担当ししっかりと会を運営していました。1年生は、思い出のさんぽを歌い、一人一人が感謝の気持ちを話し、最後にランドセルメッセージで感謝の気持ちをあらわしました。2年生は、思い出の曲を踊って感謝の気持ちをあらわし、最後は6年生も一緒に楽しく踊りました。3年生は6年生一人一人に関するクイズと歌で感謝の気持ちをあらわしました。4・5年生は思い出の先生のサプライズビデオメッセージとクイズ、歌で感謝の気持ちをあらわしました。最後は6年生が1~5年生の出し物へのお礼を話し、自分たちの6年間を振り返るクイズで会場のみなさんへの感謝の気持ちをあらわしました。最後の最後にサプライズゲストとして本校PTA会長が地域のピアニストと一緒に登場し、6年生と保護者、在校生に向けて「太陽のような人でありたい」の歌のプレゼントをしました。感謝の気持ちが溢れる、とても良い6年生を送る会になりました。
1月集会
1月16日(木)から後期後半が始まり、子どもたちの元気な声が学校に戻ってきました。鶴小タイムに1月集会を行い、校長先生は、後期後半はまとめの時期になるので、やり残したことがないよう(特に6年生)過ごしましょう。とお話しし、児童会事務局の児童は、風邪等ひかないように元気に過ごしましょうとお話ししました。健康第一で残りの学年を元気に楽しく過ごし、学習等しっかりまとめていける後期後半にしていきましょう。今年もよろしくお願いいたします。
鶴居村音楽祭
11月22日(金)に鶴居村音楽祭の各学校訪問がありました。鶴居村在住の指揮者石川さん、そして今年もヴァイオリンの成田さん、チェロの上村さん、ピアノの中野さん、今年初めてメゾ・ソプラノ歌手の林さんの5名が来校され、今年も楽しい音楽と語りをきかせてくれました。最後は子どもたちと校歌を指揮・演奏してくださり、林さんと一緒に全校で歌うことができました。プロの音楽を身近に聴く・体験できる貴重な時間となりました。
釧路管内PTA連合会研究大会鶴居村大会・子育て研修会
11月10日(日)に釧路管内PTA連合会研究大会鶴居村大会が、鶴居村総合センターで行われました。鶴居小学校PTAがこの大会の事務局校ということで、この日に向けて様々な準備を進めてきました。9日(土)に前日の準備・リハーサルをして、当日を迎えました。釧路管内やその他の地域からもこの研究会に参加していただき、300人を越える人数が集まりました。研究会の講演会ではスピードスケートオリンピック金メダリストの髙木菜那さんから、「なな転び八起~わたしが今伝えたいこと~」の演題でお話しをいただきました。親はレールではなくガードレールにということで、レールを敷くのではなく、幅をもたせたガードレールになることで、子の「自己選択」「自己決定」の機会をもつことにつながり、自立した子に成長していくのではといった本人の子ども時代の経験をまじえたお話しは大変印象に残りました。また、前回のオリンピックについても触れ「誹謗中傷」がどれだけ人を傷つけるかについても経験をもとにお話しいただき、大変心に残るお話しでした。また、子育て研修会では地元の名店サンライトファームの齊藤紀子さんを講師にお招きし体験講座「季節の食材を使ったリゾットづくり」を行いました。参加した方からは、「楽しかったし、おいしかった」「食育について改めて考える機会になった」という感想が多く寄せられました。数年ぶりの集合形式での開催で、難しさもありましたが、PTAの研修をする機会を鶴居小のPTAが中心となって進めることができたという実感が残ったすばらしい機会になりました。鶴居村PTA連合会にみなさん、鶴居小学校PTAのみなさん、ご協力、ご参加いただき本当にありがとうございました。
兵庫県市川町立鶴居小学校と交流
10月25日(金)に4年生が兵庫県市川町立鶴居小学校の4年生とオンラインで交流学習を行いました。同じ学校名の鶴居小学校とは以前からの交流があります。今回の内容は、お互いの自己紹介、そして鶴居村の鶴居小学校が総合的な学習の時間に調べた釧路湿原の動植物についてクイズ形式で兵庫の鶴居小学校の子たちに向けて発表しました。釧路湿原の動植物に兵庫県の鶴居小学校の子どもたちも興味津々の様子で、最後の感想発表も「いろいろなことが知れてよかった。」「北海道に行ってみたくなった。」という声がたくさん聞かれました。その感想を聞いた鶴居村の鶴居小学校の子どもたちはうれしそうな様子でした。次回は兵庫県の鶴居小学校が調べたことを発表してくれます。両校の子どもたちにとってとても楽しく有意義な時間になりました。兵庫県の鶴居小学校から今年も学校で育てたさつまいもをいただきました。ありがとうございました。
大成功!!学習発表会②
前回に引き続き学習発表会についてお知らせします。3年生までの発表が終了し、次は全校による心を一つに「タンチョウソーラン」です。踊るスペースを確保するために、前方のござ席を一旦片づけないといけないのですが、そこで観ていた保護者の方々は素早くござをあけて、さらにはござを丸めてくれる方もいらして、すばらしい保護者の方々だなと改めて感じた場面でした。終了後も保護者の方々のたくさんのお手伝いがありました。本当にありがとうございました。そんな中で始まったタンチョウソーラン学習発表会バージョンですが、運動会等とは一味違ったフォーメーションになっていて、見ごたえがあったり、掛け声も大きく聞こえたりととても良い発表になりました。高学年バージョン、全校バージョンどちらもかっこよかったです。次は、4・5年生による「鶴居スカイトレイン」です。スカイトレインに乗って世界中を旅する内容になっていて、行った国の音楽をリコーダー等で奏でていてとても良い構成になっていると感じました。何度も練習を重ねてきた器楽「ルパン三世のテーマ」や歌「ハローシャイニングブルー」は本番が一番よい発表になっていたと感じました。次は、6年生による「小学校生活の助け合い」です。自分たちで内容や構成を考えて取り組んだ劇やダンスがとても良かったです。器楽のメドレーや最後の8人全員でのダンスも練習の成果がしっかりと表れていました。次は、全校による合唱「鶴居小学校校歌」「飛びたてタンチョウ」です。元気な歌声の校歌、そしてきれいで雄大な飛びたてタンチョウどちらも本当にすばらしかったです。飛びたてタンチョウは取材に来られた新聞社の方もすばらしい曲だと感動していました。最後は、6年生による「終わりの言葉」です。各学年の発表の良かったところを的確に話していたり、これからの抱負を話したりと最後にふさわしい6年生の発表でした。この学習発表会に向けた取り組みや練習、観てくれる方々のことを考えた工夫等はこれからの学校生活でも必ず生きてきます。保護者の皆様、地域の皆様、観に来ていただいたすべての方々に感謝いたします。ありがとうございました。